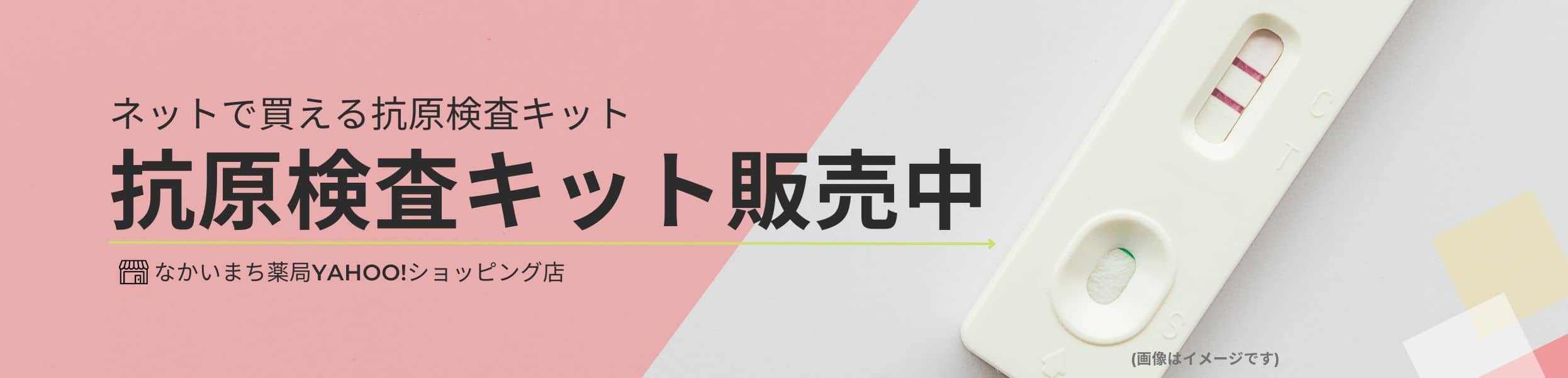膝の痛みの原因を徹底解説|症状別の見分け方と効果的な対策法

「階段を降りる時に膝がズキッと痛む」「正座ができなくなった」「立ち上がる時に膝がカクンとなる」
このような膝の痛みを感じていませんか? 膝の痛みには様々な原因があり、原因を正しく理解することが適切な対策への第一歩です。
実は膝の痛みは年齢に関係なく、 日常生活の積み重ねによって誰にでも起こりうる症状です。放置すると症状が悪化し、日常生活に支障がでることもありますが 早期の対策で予防・改善が可能です。
この記事では、 膝の痛みの主な原因から症状別の見分け方、効果的な対策法まで詳しく解説します。「これって何が原因?」と不安に感じている方は、ぜひ参考にしてください。
膝の痛みの主な原因7つ
変形性膝関節症
変形性膝関節症は 膝の痛みの原因として最も多く見られる疾患です。加齢とともに 関節の軟骨がすり減り、骨同士がこすれることで痛みが生じます。50代以降に発症しやすいですが、40代でも症状が現れることがあります。
この疾患の特徴的な症状として、 階段の下りで強く痛む、 正座ができない、膝がポキポキ鳴る、 朝起きた時の膝のこわばり、立ち上がり時の違和感、長時間歩くと痛みが増すなどがあります。
発症しやすいのは 50代以降の女性で、 男性の約4倍多く発症します。 肥満気味の方、 O脚・X脚の方、膝に負担のかかる仕事をしている方、遺伝的要因がある方もリスクが高くなります。

筋力低下・柔軟性不足
現代人に増加している膝の痛みの原因として、 筋力低下と柔軟性不足があります。太ももの前後の筋肉である 大腿四頭筋やハムストリングス、お尻の筋肉である 大臀筋が弱くなると、 膝関節を支える力が低下し、関節に直接負担がかかります。また、筋肉や靭帯の柔軟性不足も膝の痛みの重要な原因となります。
症状として、長時間歩くと膝が痛む、階段の上り下りがつらい、 膝がグラグラする不安定感、運動後の膝の痛み、膝周辺の重だるさなどが現れます。
筋力低下の主なリスク要因として、 慢性的な運動不足、 長時間のデスクワーク、加齢による自然な筋力低下、過去の怪我による活動量減少などがあります。
半月板損傷
半月板は 膝関節のクッションの役割を果たす軟骨組織で、スポーツでの急な動きや日常生活でのしゃがみ込み動作などで損傷することがあります。 若い世代から中高年まで幅広い年代で発症する膝の痛みの原因です。
主な症状として、 膝が「カクン」と外れるような感覚、膝の曲げ伸ばしが困難、 膝に水が溜まる関節水腫、膝の内側または外側の限局的な痛み、 膝のロッキング現象があります。
損傷を起こしやすい動作には、 急な方向転換、ジャンプからの着地、深いしゃがみ込み動作、膝をひねる動作、体重をかけた状態での回転動作などがあります。
体重増加による膝への負担
体重増加は見過ごされがちですが、 膝の痛みの重要な原因です。 体重が1kg増えるごとに、歩行時は 膝に約3~4倍の負荷がかかると言われています。階段の下りでは、さらに大きな負担となります。
体重増加後の膝の違和感、長時間立っていると痛む、歩き始めの痛み、夕方になると膝が重いなどの症状が現れます。体重増加の背景には、食生活の変化、運動不足、代謝の低下、ストレスによる過食などがあります。
冷え・血行不良
特に女性に多い膝の痛みの原因として 冷え・血行不良があります。 膝周辺の血流が悪くなると、筋肉や関節に必要な酸素や栄養が届きにくくなり、老廃物も蓄積しやすくなります。その結果、痛みやこわばりを感じやすくなり、回復も遅れてしまいます。
寒い日や朝の膝のこわばり、膝の重だるさ、夜間の膝の痛み、膝を触ると冷たいなどの症状が特徴的です。冷えの主な原因として、筋肉量の不足、自律神経の乱れ、血管の収縮、服装による冷えなどがあります。
姿勢・歩き方の問題
悪い姿勢や間違った歩き方のクセにより、膝関節に偏った負担がかかり続けることで痛みが生じます。特に O脚やX脚は、 関節の片側に負荷が集中し、痛みや変形の原因となります。
問題となる姿勢や歩き方として、O脚・X脚、猫背での歩行、ガニ股歩き、内股歩き、かかと重心の立ち方などがあります。また、長時間の正座、深いしゃがみ込み、急な立ち上がり、重い荷物を持った歩行なども 膝に負担をかける日常動作です。

ホルモンバランスの変化
特に女性に影響する膝の痛みの原因として、 ホルモンバランスの変化があります。女性ホルモンである エストロゲンの減少により、筋力低下や靭帯の支持力低下が起こります。また、 骨密度の低下も膝関節への負担を増加させる要因となります。
影響を受けやすい時期として、 更年期、 産後の回復期、月経不順時、過度なダイエット後などがあります。ホルモン変化による影響には、筋肉量の減少、靭帯の柔軟性低下、骨密度の減少、関節液の質の変化などがあります。
症状別:膝の痛みの原因診断
あなたの膝の痛みがどの症状に当てはまるかを確認してみましょう。 症状によって考えられる原因が異なります。
階段を降りる時に痛む

階段の下りで痛む場合、 最も可能性が高い原因は変形性膝関節症です。階段の下りは膝に体重の約3~4倍の負荷がかかるため、軟骨の摩耗が進んでいると痛みが出やすくなります。これは 変形性膝関節症の最も典型的な症状の一つです。その他の可能性として、膝蓋骨軟化症、腸脛靭帯炎、筋力低下なども考えられます。
朝起きた時に膝がこわばる

朝起きた時に膝がこわばる場合、変形性膝関節症による 関節の炎症反応や、夜間の血流低下による冷え・血行不良が原因として考えられます。 複数の関節に症状がある場合は、関節リウマチの可能性も検討する必要があります。
膝がギシギシ音がする

膝からギシギシ音がする場合、変形性膝関節症による 軟骨の摩耗による摩擦音の可能性が高くなります。 関節液の減少による潤滑不足や、軟骨の表面の粗さによる滑らかさの低下も原因として考えられます。
正座ができない

正座ができない場合、変形性膝関節症による 関節の変形により可動域が制限されている可能性があります。また、半月板損傷による膝の曲げ伸ばしの支障や、 長期間の運動不足による膝関節の柔軟性低下も原因として考えられます。
運動後に膝が痛む

運動後に膝が痛む場合、 膝を支える筋力不足、使いすぎによる炎症である オーバーユース、不適切な運動フォームによる膝への過度な負担などが原因として考えられます。
立ち上がる時に「カクン」となる

立ち上がる時に膝がカクンとなる場合、 半月板損傷で半月板が引っかかっている可能性があります。また、 太ももの筋力不足や靭帯の緩みによる膝の安定性低下も原因として考えられます。
原因別の対策・改善法
膝の痛みの原因に応じた効果的な対策方法をご紹介します。 原因を特定した上で、適切なアプローチを選択することが改善への近道です。
変形性膝関節症の対策
変形性膝関節症の対策では、まず 体重管理が基本となります。 BMI25未満の維持を目標とし、 月1~2kg程度のペースで減量することで、膝への負担を大幅に軽減できます。
筋力強化運動

筋力強化運動では、 太ももとお尻の筋肉を重点的に鍛えます。壁スクワットは、壁に背中をつけて立ち、ゆっくりと膝を90度まで曲げて30秒キープし、3回を2セット行います。椅子を使った膝伸ばし運動では、椅子に座り片足をゆっくり伸ばして5秒キープして下ろし、左右各10回を3セット行います。
ストレッチ

ストレッチでは 関節の可動域を維持・改善します。太もも前のストレッチは、立って片足を後ろに曲げ、足首を手で持って太ももを伸ばし、15秒間を左右2回ずつ行います。太もも後ろのストレッチは、椅子に座り片足を前に伸ばし、つま先を上げて前傾姿勢をとって15秒間を左右2回ずつ行います。
温熱療法

温熱療法として、 38~40℃のお風呂に10~15分入浴し、温湿布の使用や温感サポーターの活用も効果的です。
半月板損傷の対策
半月板損傷の急性期では、 RICE処置を行います。安静にして無理な動作を避け、15~20分の氷冷を行い、弾性包帯で適度に圧迫し、可能な限り膝を心臓より高く保ちます。
回復期では、 段階的な運動復帰を目指し、特に大腿四頭筋の筋力強化を重点的に行います。バランス訓練も重要で、再発予防のための動作指導も受けることをお勧めします。

筋力低下の改善
筋力低下の改善では、 効果的な筋力トレーニングを継続的に行います。大腿四頭筋の強化として、タオルはさみ運動を行います。太ももにタオルを挟み、10秒間強く挟み続けることを10回、3セット行います。
ハムストリングスの強化では、ヒップリフトを行います。仰向けに寝て膝を立て、お尻を持ち上げて3秒キープし、10回を3セット行います。
大臀筋の強化では、横向き足上げを行います。横向きに寝て上の足を上げ、3秒キープして下ろすことを左右各10回、2セット行います。
体重管理による膝痛改善
体重管理では、 膝に負担の少ない有酸素運動を選択します。 水中ウォーキングは浮力で膝への負担を軽減でき、自転車漕ぎは膝関節に優しい運動です。椅子に座ったまま可能な上半身中心の運動も効果的です。
食事管理では、カロリー収支をマイナスにしながら、筋肉維持のために十分なたんぱく質を摂取し、膝に良い栄養素を意識して摂取します。
生活習慣の改善として、7~8時間の十分な睡眠、ストレス管理、規則正しい食事時間を心がけます。

冷え・血行不良の改善
冷え・血行不良の改善では、 入浴方法を工夫します。38~40℃のぬるめのお湯に10~15分入浴し、血行促進効果のある入浴剤を活用します。
マッサージでは、膝周辺を円を描くように優しくマッサージし、太ももの筋肉をほぐします。1日5~10分程度が目安です。
保温グッズとして、レッグウォーマー、膝掛け、温感サポーターを活用します。軽い運動として、足首の回し運動、ふくらはぎの筋肉を動かす運動、痛みのない範囲での階段昇降を行います。
日常生活で気をつけるべきポイント
膝の痛みを悪化させないための日常生活のコツを実践することで、症状の改善と予防につながります。
正しい歩き方

膝に優しい歩き方では、まず姿勢を正すことが重要です。背筋を伸ばし軽く胸を張り、顎を軽く引いて肩の力を抜きます。
足の運び方では、 かかとから着地してつま先で蹴り出し、歩幅は肩幅程度を意識し、膝を軽く曲げながら歩きます。筋肉の使い方では、太ももとお尻の筋肉を意識し、腹筋に軽く力を入れ、腕を自然に振ります。
階段の使い方

階段を上る時は、 手すりを使用し、太ももの筋肉を意識して踏み込み、一段ずつしっかりと足をつけ、痛い方の足は後から上げます。
階段を下りる時は、必ず手すりを使用し、ゆっくりと体重をかけ、膝を曲げすぎないよう注意し、痛い方の足から先に降ります。
座り方・立ち方

椅子から立ち上がる時は、椅子の前方に座り直し、両手で椅子の肘掛けや座面を支え、 太ももとお尻の筋肉で立ち上がり、勢いをつけて立ち上がらないようにします。
座る時は、 膝が90度になる高さの椅子を選び、深く腰掛け、足裏全体を床につけます。
荷物の持ち方

荷物の持ち方では、 重い荷物は両手に分けて持ち、リュックサックを活用して背中で重量を支え、重い買い物の際にはキャリーカートを使用し、長距離移動時には小まめに荷物を置いて休憩を取ります。
家事での注意点

掃除機をかける時は、前傾姿勢を避け、柄の長い掃除機を使用し、小まめに休憩を取ります。洗濯物を干す時は、洗濯かごを高い位置に置き、しゃがみ込みを避け、台を使って高さを調整します。料理をする時は、調理台の高さを適切に設定し、疲れたら椅子に座り、重い鍋は両手で持ちます。
おすすめのサポートアイテム
膝の痛みを和らげ、日常生活をサポートするアイテムを適切に選択することで、症状の改善と生活の質の向上が期待できます。
市販薬
痛み止めとして NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)が効果的です。代表的なロキソプロフェンやイブプロフェン等は鎮痛・消炎作用があり、急な痛みや炎症に使用されます。胃腸への負担を減らすため、なるべく食後に飲むようにしましょう。どうしても食後に飲めない時は多めの水で飲むようにしましょう。
外用薬では、 ボルタレンEXゲルが強い抗炎症作用を持ち、腫れや炎症が強い時に使用され、全身への影響が少ない利点があります。 温感湿布は血行促進と筋肉の緊張緩和に効果があり、慢性的な痛みや冷えによる痛みに使用されますが、入浴前後は避ける必要があります。
サポーター
薄手タイプのサポーターは日常使いに適しており、温感効果が得られ、動きやすさを重視し、長時間装着が可能です。 しっかり固定タイプはスポーツや長時間の立ち仕事に適しており、膝関節をしっかりと支えます。
サポーター選択時は、 着け心地、蒸れにくさ、着脱のしやすさをチェックすることが重要です。適切なサイズを選び、長時間装着する場合は定期的に外して血行を促進させることも大切です。
サプリメント
グルコサミンやコンドロイチンは、体内で軟骨や関節部分に多く含まれる成分で、日常生活の動きや歩行を支える役割があるとされています。一般的には、摂取を続ける場合は3ヶ月以上の継続が目安とされています。
MSM(メチルスルフォニルメタン)は、たんぱく質と結合して組織の柔軟性を保つ働きがあるといわれています。
また、コラーゲンペプチドやヒアルロン酸は、関節部の滑らかな動きに関与する成分として知られています。
サプリメントは食品からの摂取だけでは不足しがちな成分を補う役割があり、継続的な摂取が重要です。ただし、効果には個人差があり、他の薬との相互作用にも注意が必要です。
病院受診が必要な膝痛の症状
膝の痛みには自宅でのセルフケアで改善できるものと、 専門医の診断と治療が必要なものがあります。適切なタイミングで受診することで、症状の悪化を防ぎ、より効果的な治療を受けることができます。
緊急性の高い症状
膝が腫れて熱を持っている場合、膝関節内に炎症や感染が起こっている可能性があり、早急な医療処置が必要です。 強い痛みで歩けない状況や、膝が完全に曲がらない・伸びない状態は、重篤な損傷や機械的な問題が生じている可能性があります。 膝がグラグラして不安定な状態は、靭帯の断裂や重度の損傷が疑われます。

継続的な症状での受診目安
夜も痛くて眠れない状況が続く場合や、日常生活に支障をきたす程度の痛みがある場合は、専門医の診断を受ける必要があります。 市販薬が効かない状態や、 症状が2週間以上続いている場合も、適切な医療処置が必要です。
痛みの程度が徐々に悪化している場合や、膝の可動域が明らかに制限されている場合、膝に水が繰り返し溜まる場合なども、専門的な診断と治療が必要な状況です。
受診時に伝えるべき情報
医師に正確な診断をしてもらうために、 痛みの場所を具体的に伝えることが重要です。膝の内側、外側、前面、後面のどこが痛むかを明確にしましょう。痛みの種類についても、ズキズキ、ジンジン、鈍痛、刺すような痛みなど、できるだけ詳しく表現します。
痛むタイミングも重要な情報です。動作時に痛むのか、安静時に痛むのか、夜間に痛むのかを明確に伝えます。発症のきっかけについて、転倒やスポーツでの怪我、特に心当たりがない場合などの状況を説明します。
これまでの治療経過として、使用した薬の種類や効果、受けた治療の内容、他の医療機関での診断結果などを整理して伝えることで、より適切な治療方針を決定してもらえます。
まとめ
膝の痛みには多様な原因がありますが、最も大切なのは早期の対策です。軽い違和感を感じた段階で適切なケアを始めることで、将来にわたって膝の健康を維持できます。
変形性膝関節症、半月板損傷、筋力低下、体重増加、冷えや血行不良、姿勢の問題、ホルモンバランスの変化など、複数の原因が重なることも多いため、総合的なアプローチが必要です。
日常生活では、まず正しい姿勢と歩き方を心がけましょう。大腿四頭筋、ハムストリングス、大臀筋を鍛える筋力トレーニングを継続し、体重管理に取り組み、温熱療法や入浴で膝を温めることが大切です。
また、階段の使い方、立ち座りの動作、荷物の持ち方、家事の際の姿勢など、膝に負担をかけない日常動作を身につけることで、症状の改善と予防につながります。
症状に応じて、市販薬(NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)、外用薬、温感湿布)、サポーター、サプリメントなどを適切に活用することも効果的です。ただし、夜間の痛みで眠れない、市販薬が効かない、症状が2週間以上続くといった場合は、迷わず専門医に相談してください。
膝は私たちの活動的な生活を支える重要な関節です。日頃から予防とケアを心がけ、痛みや違和感を感じたときは早めに対処することで、いつまでも健康な膝を保つことができます。気になる症状があるときは、一人で悩まず専門医に相談し、適切な治療を受けて、より良い生活の質を維持していきましょう。
監修漆畑俊哉(薬剤師)

- 株式会社なかいまち薬局 代表取締役社長
- 日本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師
- 日本在宅薬学会 バイタルサイン エヴァンジェリスト
- 在宅療養支援認定薬剤師