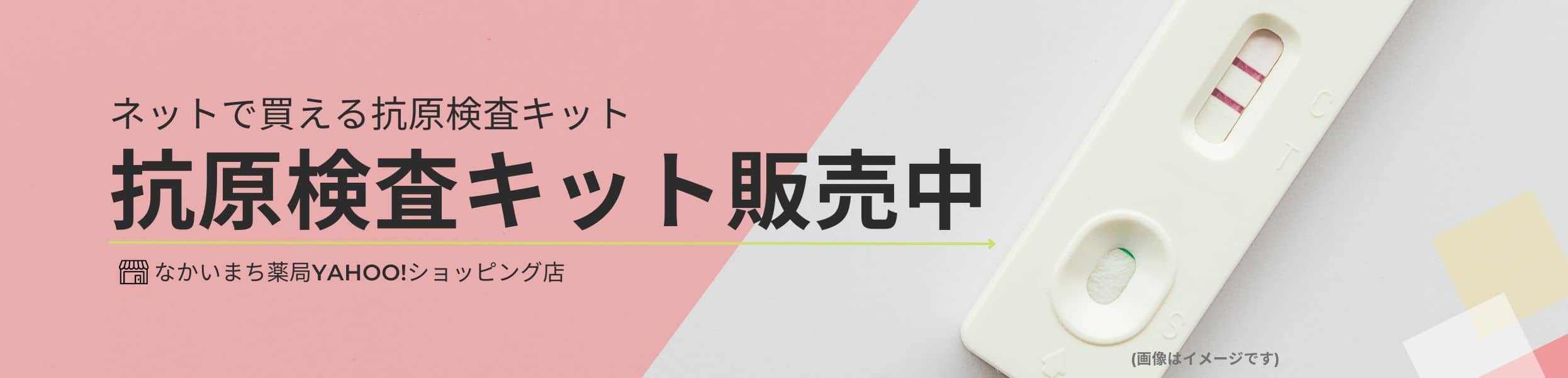季節の変わり目に気をつけたい「咳とアレルギー」対策
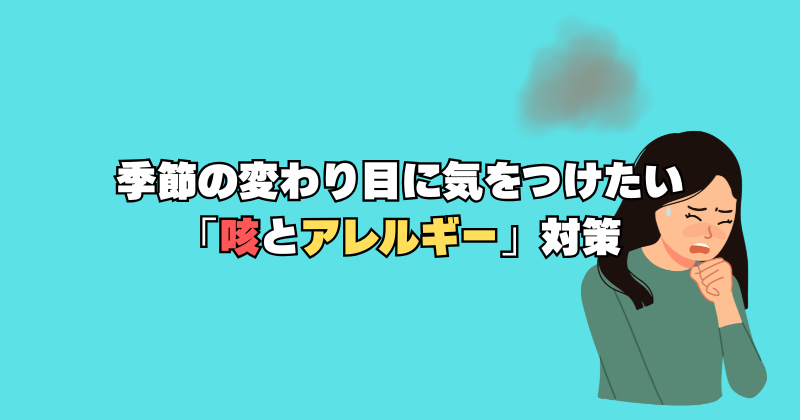
朝晩の空気がひんやりと感じられるようになり、秋の訪れを肌で実感する季節になりました。朝晩と日中の寒暖差が大きくなるこの時期、「体がだるい」「朝起きると喉が痛い」といった体調の変化を訴える方が増えています。
最近、薬局にも「急に咳が出る」「鼻がムズムズする」「透明な鼻水が止まらない」といった症状を相談に来られる方が増えています。このような症状には、風邪以外にも花粉症や寒暖差による鼻炎など、さまざまな原因があります。症状に応じた適切な対処をするためには、まず何が原因なのかを知ることが大切です。症状が長引くときは、医療機関で相談することをおすすめします。
本記事では、秋に悪化しやすい咳やアレルギー症状について薬剤師の視点から解説し、日常生活で取り入れやすい予防法や市販薬の選び方をご紹介します。
目次
なぜ秋に喘息やアレルギーが悪化しやすいの?
秋は「寒暖差」「空気の乾燥」「アレルゲンの増加」といった複数の要因が重なることで、体調を崩しやすくなる季節です。こうした環境変化が喘息やアレルギーの悪化に関与していると考えられています。
寒暖差による自律神経の乱れ

朝晩は冷え込むのに、日中は夏のような暑さになることもあります。急な気温差は自律神経に負担をかけ、体温調整や免疫バランスが乱れることで、アレルギー症状や咳が出やすくなります。
秋に増えるアレルゲン

ブタクサやヨモギなどの秋の花粉に加え、ダニは一年中存在し、その死骸や糞は通年性アレルギーの原因となります。秋は湿度低下により、これらが舞い上がりやすくなる時期です。これらのアレルゲンは、くしゃみや鼻水、咳の原因となります。
生活リズムの乱れによる免疫低下
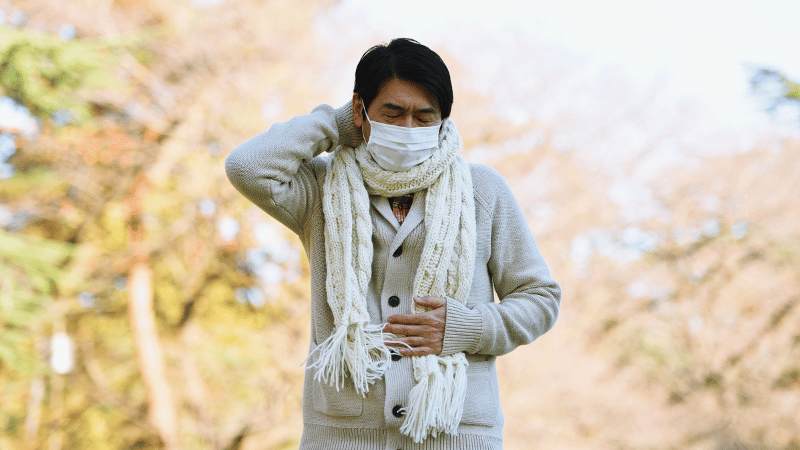
夏の暑さが和らぎ、日照時間も短くなる秋は、寝不足や食欲の変化、運動不足などで生活リズムが乱れやすい季節です。こうした生活習慣の変化は、自律神経やホルモンバランスに影響を与え、自律神経のバランスが乱れて、症状が出やすい体質になってしまうことがあります。
乾燥による粘膜の防御力低下

空気の乾燥は鼻や喉の粘膜を敏感になりやすくさせ、防御機能の低下を招きます。乾いた粘膜は花粉やホコリなどの刺激に敏感になり、アレルギー反応を引き起こしやすくなります。
寒暖差アレルギーとは?血管運動性鼻炎との違いと対策
「寒暖差アレルギー」は正式な医学用語ではありませんが、一般的には「血管運動性鼻炎」や「非アレルギー性鼻炎」として知られています。これは気温差によって鼻粘膜が刺激されることで起こる反応で、自律神経の乱れが関係しています。
以下のような症状が見られる場合、寒暖差による影響が疑われます。
- 水のような鼻水が出る
- くしゃみが何度も出る
- 鼻づまりがある
- 喉がイガイガしたり、咳が出たりする

喘息と咳喘息の違い
咳が長引く場合、風邪ではなく「喘息」や「咳喘息」の可能性もあります。
喘息とは
気道の慢性的な炎症によって、呼吸時にヒューヒュー・ゼーゼーという音がしたり、息苦しさや咳が出たりする疾患です。夜間や明け方に症状が強まることがあり、アレルゲンやストレス、風邪が引き金になる場合もあります。
咳喘息とは
喘鳴を伴わず、乾いた咳が長く続くタイプの喘息で、気道の軽度な炎症が関与しています。医療現場では、咳が3週間以上続く場合には、咳喘息などの可能性も考えられます。8週間以上続くと「慢性咳嗽」と呼ばれ、呼吸器専門医への相談が推奨されます。
治療のポイントと薬の見直し
症状に合った薬を使用することが重要です。市販薬の使用についても、医師や薬剤師に相談の上で選びましょう。
アレルギー性鼻炎・寒暖差アレルギー向けの薬
アレグラFX(フェキソフェナジン)
第2世代抗ヒスタミン薬で、眠気が少なく日中の使用に向いています。
ナザールAR
ステロイド成分配合の点鼻薬で、鼻粘膜の炎症を抑える効果があります。継続使用により効果が発揮されます。
小青竜湯(しょうせいりゅうとう)
寒くなると鼻水が出やすくなる方に、昔から使われている漢方薬です。お体に合うかどうかは個人差がありますので、薬剤師にご相談ください。
咳や喘息症状向けの薬
新コンタックせき止めダブル
長時間作用型の鎮咳薬で、夜間の咳がつらい方にも適しています。ただし、他の薬との併用や長期使用には注意が必要です。
麦門冬湯(ばくもんどうとう)
から咳やのどの乾燥が気になる方に、伝統的に用いられてきた漢方薬です。症状の原因によって適したお薬が変わりますので、薬剤師にお尋ねください。
薬の見直し、こんな点に注意
症状に合っているか?
季節の変化に合わせて薬も見直す必要があります。効きにくさを感じたら薬剤師にご相談ください。
吸入薬の使用方法は正確か?
吸入方法が誤っていると、薬の効果が十分に発揮されません。例えば「エアゾール式」や「ドライパウダー式」の吸入器は、それぞれ使い方が異なります。不安がある場合は、薬剤師に実際の使用方法を確認することをおすすめします。
自己判断で中止していないか?
症状が軽くなっても、自己判断で薬を中断すると悪化する恐れがあります。必ず医師や薬剤師の指示に従ってください。
薬の保管状態は適切か?
直射日光や高温多湿を避けて保管しましょう。特に液体薬や漢方薬は劣化しやすいため、期限や保存状態を定期的に確認してください。
日常生活でできる予防策
室内環境の整備
加湿器を使い、室内湿度を50〜60%に保つことで粘膜を保護し、アレルゲンへの過敏反応を和らげる効果が期待できます。
掃除と換気の徹底

アレルゲンとなるホコリやカビは、見えない場所にも蓄積しています。週に2-3回の掃除機がけに加え、エアコンのフィルターや家具の隙間、カーテンなども定期的に清掃しましょう。また、1日に数回、5-10分程度の換気を行うことで、室内の空気を新鮮に保ち、湿度調節にも効果的です。特に料理後や入浴後は、湿気がこもりやすいため積極的な換気を心がけてください。
寝具のケア

寝具は1日の3分の1を過ごす重要な環境です。週に1回は布団を天日干しし、布団乾燥機を月2回程度使用することでダニの繁殖を抑制できます。枕カバーやシーツは週に1回、布団カバーは2週間に1回を目安に洗濯し、可能であれば60℃以上の高温で洗うとダニ対策に効果的です。ただし、家庭用洗濯機での高温洗浄が難しい場合は、布団乾燥機や布団専用クリーナーを併用すると効果的です。
体調管理
十分な睡眠

質の良い睡眠は、自律神経のバランスを整え、免疫力を維持する最も重要な要素の一つです。理想的な睡眠時間は7-8時間で、毎日同じ時間に就寝・起床することで体内時計を整えます。就寝前のスマートフォンやテレビは控え、室温は18-22℃、湿度50-60%を保つことで快適な睡眠環境を作りましょう。寝室の換気も忘れずに行い、清潔な空気の中で休息を取ることが大切です。
バランスの良い食事

粘膜の健康維持には、バランスの取れた栄養摂取が欠かせません。ビタミンA(緑黄色野菜)は粘膜を強化し、ビタミンC(柑橘類・ブロッコリー)は免疫力を高めます。良質なたんぱく質(魚・鶏肉・豆類)は体の修復に必要で、亜鉛(牡蠣・ナッツ類)は免疫機能をサポートします。また、発酵食品(ヨーグルト・納豆)で腸内環境を整えることも、全身の免疫力向上につながります。1日3食、規則正しい食事を心がけましょう。
適度な運動

適度な運動は血行を促進し、自律神経のバランスを整える効果があります。1日20-30分程度のウォーキングや軽いストレッチから始め、週3-4回継続することを目標にしましょう。階段の上り下りや家事での体の動きも立派な運動になります。
ただし、激しい運動は免疫力を一時的に低下させることがあるため、「少し汗ばむ程度」を心がけてください。屋外での運動時は花粉やアレルゲンに注意し、マスクの着用や帰宅後の手洗い・うがいを忘れずに行いましょう。運動後の十分な水分補給も、粘膜の乾燥を防ぐために重要です。
気温差対策
衣類で調整

季節の変わり目は1日の気温差が10℃以上になることもあるため、重ね着による細かな体温調節が重要です。薄手のカーディガンやストール、ベストなど着脱しやすいアイテムを活用し、外出先でも快適に過ごせるよう準備しましょう。
特に首、手首、足首の「3つの首」は太い血管が通っているため、ここを温めることで全身の血行が改善されます。
腹部の冷えは自律神経の乱れにつながりやすいので、薄手の腹巻きやインナーで保温することをおすすめします。素材は吸湿性と通気性に優れた天然繊維を選ぶと、汗をかいても快適に過ごせます。
就寝時の冷え防止

就寝中の体温低下は、自律神経のバランスを崩し、朝の咳や鼻水の原因となることがあります。腹巻きやレッグウォーマーを着用することで、体の中心部と末端の冷えを防ぎ、質の良い睡眠を確保できます。寝具選びも重要で、羽毛布団や毛布の重ね方を季節に応じて調整しましょう。
足元が冷えやすい方は、湯たんぽや電気毛布を就寝前に使用して布団を温めておくと効果的です。ただし、寝汗をかくほど温めすぎると、かえって体調不良の原因となるため、快適と感じる程度の保温を心がけてください。
まとめ
秋は体調を崩しやすい季節ですが、原因を理解し、日々の生活の中でできる対策を実践することで、症状の予防や軽減につながります。
症状でお困りのときは、まず薬剤師にご相談ください。市販薬の選び方や使い方について適切にアドバイスいたします。症状が続く場合は医療機関を受診して、適切な診断を受けて根本的な治療につなげることが大切です。また、処方されたお薬についてご質問があるときも、安心してお使いいただけるよう薬剤師がサポートいたします。
なお、この記事でご紹介している内容は、一般的な健康情報をお伝えするものです。実際の診断や治療については、必ず医療機関で医師の診察をお受けください。お一人お一人の症状に最も適した対応をしていただくためです。
地域の皆さまが健やかな毎日を送れるよう、適切な医療機関との連携を大切にしながら、薬局スタッフ一同でお手伝いしてまいります。
監修漆畑俊哉(薬剤師)

- 株式会社なかいまち薬局 代表取締役社長
- 日本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師
- 日本在宅薬学会 バイタルサイン エヴァンジェリスト
- 在宅療養支援認定薬剤師